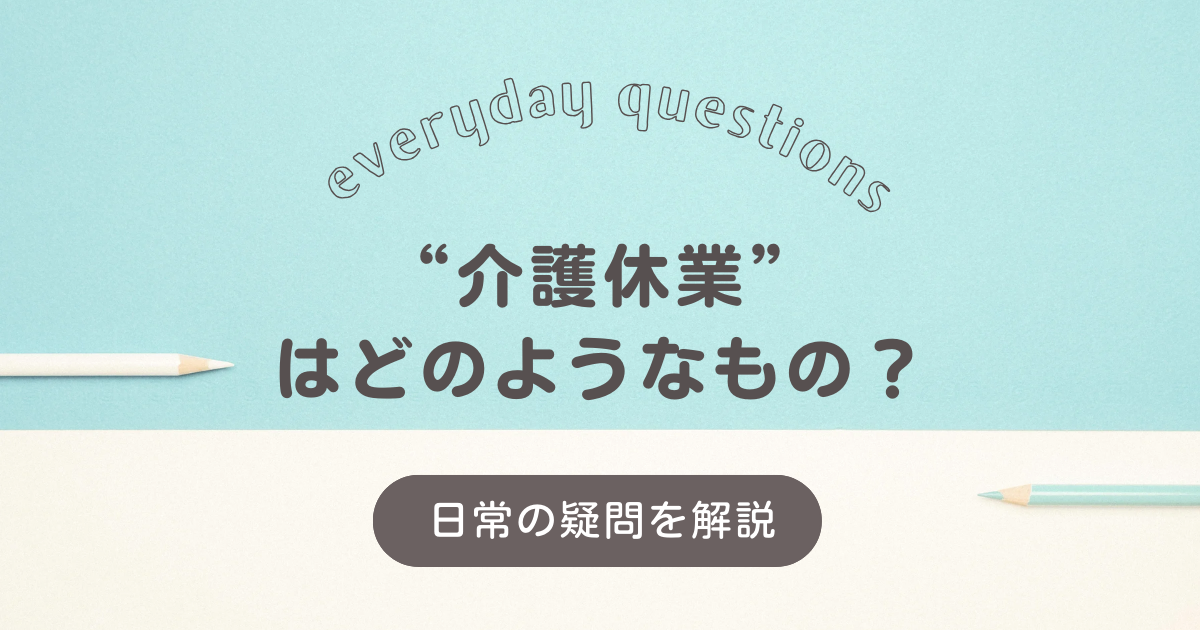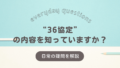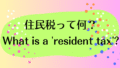介護休業は、どんなときに取得できるか知っていますか?実際に身近で、介護休業を取得されている方はいらっしゃいますか?介護離職は年10万人に達するといわれています。そのため、介護休業を身近で利用されていることはまだまだ少ないのが現状です。
今後、自分自身や周りで働く仲間が、介護休業を取得する際に備え、就業規則などで、介護休業の制度について記載されている部分をあらかじめ確認しておくことも大切です。
2025年4月には、改正育児・介護休業法が施行されます。労働者から介護の申し出があった場合、介護制度の周知や取得の意向確認が企業に義務づけられますし、介護休業等に関する研修や相談窓口の設置などの介護休業等の申出がしやすくなるような環境整備についての措置が義務づけられます。
※『育児・介護休業法の改正ポイント』の概要については、
下記のURLをご参照ください。
育児・介護休業法 改正のポイントのご案内|厚生労働省
『介護休業』とは、要介護状態にある対象家族を介護をするために休業することをいいます(育介法2条2号)。介護休業をすることができるのは、対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度として、原則として労働者が申し出た期間です(育介法11条1項、2項)。
介護休業は、労働者が現実に対象家族の介護をするために利用することを想定しているものではありません。これから現実に、介護を要する家族を支えていくための準備をするための期間です。家族の介護をしながら、自分の仕事を継続できる体制づくりのための休業期間です。市区町村、地域包括支援センターへの相談、介護の施設の下見や、情報収集などに使われることが想定されます。
『要介護状態』とは、ケガなどの負傷、病気、又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な場合をいいます。『常時介護が必要な状態』については、2つの判断基準が定められています。(1)又は(2)のいずれかに該当した場合です。
(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること
※『要介護認定』の概要について、『要介護認定』の判定については、
下記のURLをご参照ください。
『要介護認定』に係る制度の概要|厚生労働省
『要介護認定』はどのように行われるか|厚生労働省
(2)『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の表の状態①~⑫のうち、
2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続するとき
※『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の表は、下記のURLをご参照ください。
『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の表|厚生労働省
『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の表の注釈にも記載されていますが、判断をする際、基準に厳密に従うことで、労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、個々の事情に応じて、できる限り仕事と介護が両立できるような柔軟な運用が促されています。又、(1)または(2)のいずれかに該当する場合の記載の通り、必ずしも行政の要介護認定を受けていなくても、対象となります。
『要介護状態』になるかについて、要介護認定の書類や医師の診断書の提出を求める場合が多いと思われますが、各種証明書の提出は労働者に過大な負担をかけることのないよう、必要最小限度の提出とする配慮が必要になります。
例えば、市区町村が交付する介護保険被保険者証の提出を求める場合も、介護保険制度の要介護認定の判断には、少し時間がかかることも想定されます。その場合、『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の表を利用し、①~⑫の各項目について、該当する状態に○をつけてもらうことで、常時介護を必要とする状態であることを申告してもらう方法もあります。
ただし、介護休業給付金の支給申請を予定されている場合は、給付金申請に添付が必要な書類も別途ありますので、その場合は、介護休業の申し出時に提出を求めることも検討されてください。
『要介護状態にある家族』の『対象家族』は、従業員の配偶者(事実婚の人を含む)、父母、子ども、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。介護休業は高齢者の介護に限らず、医療的ケア児を介護する場合も含まれます。
※『介護休業制度』については、下記のURLをご参照ください。
介護休業について|介護休業制度|厚生労働省
介護休業は、労働者にとって初めての経験となり、これからの事を考えるとどうしたらいいか分からない等、とても不安な気持ちを抱えていらっしゃることと思われます。そして上司や会社の総務に相談をする場合も、特に仕事が繁忙期に重なる際には、申し出るにもとても勇気の伴うことも予想されます。
労働者の希望をくみとりつつ、会社としてどんなサポートができるのかを具体的に話し合える場を定期的に設けられることで、働く人にとって、安心して働ける職場になることでしょう。